| |
| |
| |
| |
食品安全・表示/健康・食育  |
| |
| 〜〜2009年発行〜〜 |
| |
 書評「食の安全−政治が操るアメリカの食卓」食の安全・監視市民委員会代表神山美智子(6/15号) 書評「食の安全−政治が操るアメリカの食卓」食の安全・監視市民委員会代表神山美智子(6/15号)
 解説「政府が温室効果ガス削減「中期目標」決定」週刊農林編集部(6/15号) 解説「政府が温室効果ガス削減「中期目標」決定」週刊農林編集部(6/15号)
 解説「2008年度 食育白書」週刊農林編集部(6/15号) 解説「2008年度 食育白書」週刊農林編集部(6/15号)
 「新型インフルエンザに備えた家庭用食料品備蓄ガイド」週刊農林編集部(5/15号) 「新型インフルエンザに備えた家庭用食料品備蓄ガイド」週刊農林編集部(5/15号)
 「卸売市場における先進的な取組み」<1〜2>週刊農林編集部(4/25号・5/25号) 「卸売市場における先進的な取組み」<1〜2>週刊農林編集部(4/25号・5/25号)
 「消費者が行動して自給率向上へ」<抄>パルシステム生活協同組合連合会専務理事唐笠一雄(4/15号) 「消費者が行動して自給率向上へ」<抄>パルシステム生活協同組合連合会専務理事唐笠一雄(4/15号)
 「バーク堆肥にカドミ低減効果」」(2/25号) 「バーク堆肥にカドミ低減効果」」(2/25号)
 「農林水産分野における省CO2効果「見える化」の展望」週刊農林編集部(1/25号) 「農林水産分野における省CO2効果「見える化」の展望」週刊農林編集部(1/25号)
新年特集
 「学校給食から発信する食育」高崎市立並榎中学校教諭 山田ミチ子/栄養士 福島智枝子(3/25号) 「学校給食から発信する食育」高崎市立並榎中学校教諭 山田ミチ子/栄養士 福島智枝子(3/25号)
 「体験に根ざした食育〜きときと氷見地消地産推進協議会」<1〜2>氷見市商工観光課澤 永貢子一(3/15号・4/25号) 「体験に根ざした食育〜きときと氷見地消地産推進協議会」<1〜2>氷見市商工観光課澤 永貢子一(3/15号・4/25号)
 「食育は小さな歩みなれど大きな力あり」栃木県農業大学校教授
齋藤一治(3/5号) 「食育は小さな歩みなれど大きな力あり」栃木県農業大学校教授
齋藤一治(3/5号)
 「食育から日本農業を応援しよう」<1〜3>滋賀大学教育学部教授
木島温夫(3/5号・3/15号・4/5号) 「食育から日本農業を応援しよう」<1〜3>滋賀大学教育学部教授
木島温夫(3/5号・3/15号・4/5号)
 「食育を通じた農山漁村の活性化」<農林抄>内閣府食育推進室主査
佐藤義典(1/15号) 「食育を通じた農山漁村の活性化」<農林抄>内閣府食育推進室主査
佐藤義典(1/15号)
 「手作りおにぎり」で育つ「農業・農家の応援団」<1〜3>農山漁村文化協会常務理事
栗田庄一(新年特集号・1/25号・2/25号) 「手作りおにぎり」で育つ「農業・農家の応援団」<1〜3>農山漁村文化協会常務理事
栗田庄一(新年特集号・1/25号・2/25号)
 「子ども達の農業に対する興味と可能性を広げる子どもファーム・ネット」 「子ども達の農業に対する興味と可能性を広げる子どもファーム・ネット」
全国子どもファーム・ネット推進協議会事務局
伊藤 悟(新年特集号)
 「とくしまみそ汁プロジェクト」<1〜2>徳島県阿波市立市場小学校教諭
藤本勇二(新年特集号・1/15号) 「とくしまみそ汁プロジェクト」<1〜2>徳島県阿波市立市場小学校教諭
藤本勇二(新年特集号・1/15号)
 「なぜ喜多方市小学校農業科がはじまったのか」<1〜3>喜多方市教育委員会課長補佐
渡部 裕(新年特集号・2/15号・2/25号) 「なぜ喜多方市小学校農業科がはじまったのか」<1〜3>喜多方市教育委員会課長補佐
渡部 裕(新年特集号・2/15号・2/25号)
 「食の大切さと喜びを伝える食育」青山学院大学教授
三村優美子(新年特集号) 「食の大切さと喜びを伝える食育」青山学院大学教授
三村優美子(新年特集号)
 「水産版食育「ぎょしょく教育」の実践と地域の連携」<1〜3> 「水産版食育「ぎょしょく教育」の実践と地域の連携」<1〜3>
愛媛大学南予水産研究センター教授
若林良和(新年特集号・1/15号・2/15号)
 「食育から日本農業を応援する」<1〜2>長崎大学大学院准教授
中村 修(新年特集号・1/25号) 「食育から日本農業を応援する」<1〜2>長崎大学大学院准教授
中村 修(新年特集号・1/25号)
 「食育が変える『農』の未来」<農林抄>農林水産省大臣官房食料安全保障課長
末松広行(新年特集号) 「食育が変える『農』の未来」<農林抄>農林水産省大臣官房食料安全保障課長
末松広行(新年特集号) |
| |
| 〜〜2008年発行〜〜 |
| |
 「非食用米・事故米の市場流通を支える減反政策」遺伝毒性を考える集い代表(10/5号) 「非食用米・事故米の市場流通を支える減反政策」遺伝毒性を考える集い代表(10/5号)
 「「事故米」食用転売」週刊農林編集部(9/25号) 「「事故米」食用転売」週刊農林編集部(9/25号)
 解説 民主党「消費者権利院制度」週刊農林編集部(9/5号) 解説 民主党「消費者権利院制度」週刊農林編集部(9/5号)
 「農産物に低炭素表示導入へ」週刊農林編集部(7/5号) 「農産物に低炭素表示導入へ」週刊農林編集部(7/5号)
 「東京都が冷凍食品に原料原産地表示導入」週刊農林編集部(5/15号) 「東京都が冷凍食品に原料原産地表示導入」週刊農林編集部(5/15号)
 「納豆の抗老化機能を実証」週刊農林編集部(4/5号) 「納豆の抗老化機能を実証」週刊農林編集部(4/5号)
 「学校給食を地産地消の「食育」の場に」お米の勉強会代表村山日南子(2/25号) 「学校給食を地産地消の「食育」の場に」お米の勉強会代表村山日南子(2/25号)
 解説「都が卸売市場手数料を自由化」週刊農林編集部(2/25号) 解説「都が卸売市場手数料を自由化」週刊農林編集部(2/25号)
 解説「学校給食法が初の抜本改定」週刊農林編集部(1/15号) 解説「学校給食法が初の抜本改定」週刊農林編集部(1/15号) |
| |
| 〜〜2007年発行〜〜 |
| |
 解説「業者間取引も原産地表示義務化」週刊農林編集部(12/25号) 解説「業者間取引も原産地表示義務化」週刊農林編集部(12/25号)
 解説「みかんで骨粗鬆症予防』」
週刊農林編集部(10/25号) 解説「みかんで骨粗鬆症予防』」
週刊農林編集部(10/25号)
 解説「内閣府『食料供給に関する世論調査』」
週刊農林編集部(2/5号) 解説「内閣府『食料供給に関する世論調査』」
週刊農林編集部(2/5号) |
| |
| 〜〜2006年発行〜〜 |
| |
 解説「食料コスト5年で2割縮減アクションプラン」週刊農林編集部(10/15号) 解説「食料コスト5年で2割縮減アクションプラン」週刊農林編集部(10/15号)
 解説「ポジティブリストがいよいよスタート」<1〜2>週刊農林編集部(4/25号・5/15号) 解説「ポジティブリストがいよいよスタート」<1〜2>週刊農林編集部(4/25号・5/15号)
 食育基本計画「学校給食へ地場産使用3割以上目標」週刊農林編集部(5/15号) 食育基本計画「学校給食へ地場産使用3割以上目標」週刊農林編集部(5/15号)
 「花粉症緩和米開発サル・ヒト試験段階に」週刊農林編集部(4/15号) 「花粉症緩和米開発サル・ヒト試験段階に」週刊農林編集部(4/15号)
 「不老長寿CoQ10含有米を開発」週刊農林編集部(2/25号) 「不老長寿CoQ10含有米を開発」週刊農林編集部(2/25号)
 「べにふうき緑茶が人と農を救う」
週刊農林編集部(2/5号) 「べにふうき緑茶が人と農を救う」
週刊農林編集部(2/5号) |
| |
| 〜〜2005年発行〜〜 |
| |
 「鳥インフルエンザ新防疫対応で生産者が反論」 週刊農林編集部(9/25号) 「鳥インフルエンザ新防疫対応で生産者が反論」 週刊農林編集部(9/25号)
 「『有機』表示も信憑性抱く」 週刊農林編集部(9/5号) 「『有機』表示も信憑性抱く」 週刊農林編集部(9/5号)
 「マーガリンが心臓病のリスク高める」 週刊農林編集部(9/5号) 「マーガリンが心臓病のリスク高める」 週刊農林編集部(9/5号)
 食生活改善に「食事バランスガイド」普及へ 週刊農林編集部(8/5号) 食生活改善に「食事バランスガイド」普及へ 週刊農林編集部(8/5号)
 概説「食育基本法」〜食を通じて生きる力を育む〜 週刊農林編集部(7/25号) 概説「食育基本法」〜食を通じて生きる力を育む〜 週刊農林編集部(7/25号)
 「食育は『完全米飯給食』から」 フーズ・アンド・ヘルス研究所代表 幕内秀夫(3/25号) 「食育は『完全米飯給食』から」 フーズ・アンド・ヘルス研究所代表 幕内秀夫(3/25号)
 「米国産牛肉解禁に向けた『月齢判別特別研究』報告」週刊農林編集部(2/5号) 「米国産牛肉解禁に向けた『月齢判別特別研究』報告」週刊農林編集部(2/5号) |
| |
| 〜〜2004年発行〜〜 |
| |
 「納豆の健康機能を医・薬・栄養学から探る」週刊農林編集部(12/25号) 「納豆の健康機能を医・薬・栄養学から探る」週刊農林編集部(12/25号)
 「有機畜産物JAS規格案の日本的特徴と今後の展望」地域社会計画センター客員研究員
横田茂永(6/25号) 「有機畜産物JAS規格案の日本的特徴と今後の展望」地域社会計画センター客員研究員
横田茂永(6/25号)
 「有機畜産物JAS規格と地域・国内自給をめざす有機畜産の展望」NPO法人「有機農業推進協会」事務局長
白根節子(6/25号) 「有機畜産物JAS規格と地域・国内自給をめざす有機畜産の展望」NPO法人「有機農業推進協会」事務局長
白根節子(6/25号)
 「人畜共通抗生物質の使用制限を」週刊農林編集部(2/15号) 「人畜共通抗生物質の使用制限を」週刊農林編集部(2/15号) |
| |
| 〜〜2003年発行〜〜 |
| |
 中教審「栄養教諭創設を提言」
週刊農林編集部(10/5号) 中教審「栄養教諭創設を提言」
週刊農林編集部(10/5号)
 「食の安全・安心のための政策大綱」
週刊農林編集部(7/5号) 「食の安全・安心のための政策大綱」
週刊農林編集部(7/5号)
 「食の安全・安心のための政策大綱」
週刊農林編集部(7/5号) 「食の安全・安心のための政策大綱」
週刊農林編集部(7/5号)
 消費者が「食の安全・監視市民委員会」設立
週刊農林編集部(6/25号) 消費者が「食の安全・監視市民委員会」設立
週刊農林編集部(6/25号)
 「消費者団体は消費者問題の『専門家』だ」
全国消費者団体連絡会事務局長
神田敏子(4/25号) 「消費者団体は消費者問題の『専門家』だ」
全国消費者団体連絡会事務局長
神田敏子(4/25号)
 「食品安全基本法への期待と危惧」
遺伝毒性を考える集い代表
亘 昌子(4/25号) 「食品安全基本法への期待と危惧」
遺伝毒性を考える集い代表
亘 昌子(4/25号)
 「期待されない食品安全基本法」
弁護士
中村雅人(4/25号) 「期待されない食品安全基本法」
弁護士
中村雅人(4/25号)
 「食品安全基本法への見解」
日本生活協同組合連合会(4/25号) 「食品安全基本法への見解」
日本生活協同組合連合会(4/25号)
 「行政責任・消費者代表機関を法改正に明記せよ」
食品安全コンサルタント
鈴木寿夫(4/15号) 「行政責任・消費者代表機関を法改正に明記せよ」
食品安全コンサルタント
鈴木寿夫(4/15号)
 「スタート点から間違っていないか!〜これでは食品安全行政の前進はない〜」
全国獣医事協議会副会長
八竹昭夫(4/5号 「スタート点から間違っていないか!〜これでは食品安全行政の前進はない〜」
全国獣医事協議会副会長
八竹昭夫(4/5号
 「食品安全基本法制定に対する期待と危惧」
弁護士
神山美智子(4/5号) 「食品安全基本法制定に対する期待と危惧」
弁護士
神山美智子(4/5号)
 解説「政府の食品安全確保に向けた新たな取組み(8法案)」<1〜3> 週刊農林編集部(2/25号・3/5号・3/15号) 解説「政府の食品安全確保に向けた新たな取組み(8法案)」<1〜3> 週刊農林編集部(2/25号・3/5号・3/15号) |
| |
| 〜〜2002年発行〜〜 |
| |
 「ポテトチップに発癌性物質」 週刊農林編集部(11/15号) 「ポテトチップに発癌性物質」 週刊農林編集部(11/15号)
 「安心できない健康食品」 週刊農林編集部(10/25号) 「安心できない健康食品」 週刊農林編集部(10/25号)
 無登録農薬問題を考える「大半の農家が『失効』知らず」 週刊農林編集部(9/25号) 無登録農薬問題を考える「大半の農家が『失効』知らず」 週刊農林編集部(9/25号)
 食品表示に関する国民生活モニター調査「8割が食品表示に不信感」
週刊農林編集部(8/25号) 食品表示に関する国民生活モニター調査「8割が食品表示に不信感」
週刊農林編集部(8/25号)
 「食品の安全性確保への改革」
食品衛生管理コンサルタント
鈴木寿夫(8/25号) 「食品の安全性確保への改革」
食品衛生管理コンサルタント
鈴木寿夫(8/25号)
 「食品安全基本法の成果の鍵は委員の人選で決まる」
全国獣医事協議会副会長
八竹昭夫(7/15号) 「食品安全基本法の成果の鍵は委員の人選で決まる」
全国獣医事協議会副会長
八竹昭夫(7/15号)
 「安全な食品を選択する権利がある」<1〜2>
遺伝毒性を考える集い代表
亘 昌子(6/25号・7/5号) 「安全な食品を選択する権利がある」<1〜2>
遺伝毒性を考える集い代表
亘 昌子(6/25号・7/5号)
 「食品安全に関する法整備」<1〜2>
弁護士
中村雅人(6/25号・7/5号) 「食品安全に関する法整備」<1〜2>
弁護士
中村雅人(6/25号・7/5号)
 「食品の安全確保のための法整備」弁護士
神山美智子(6/15号) 「食品の安全確保のための法整備」弁護士
神山美智子(6/15号)
 「食品の安全と信頼を取り戻す」市民バイオテクノロジー情報室代表
天笠啓祐(6/15号) 「食品の安全と信頼を取り戻す」市民バイオテクノロジー情報室代表
天笠啓祐(6/15号)
 食品安全確保に向けた要望・提言<1〜5> 週刊農林編集部 食品安全確保に向けた要望・提言<1〜5> 週刊農林編集部
(5/25号、6/15号、6/25号・7/5号・7/15号)
 食品偽装表示問題「消費者から『告発』期待〜食品表示110番〜」 週刊農林編集部(3/5号) 食品偽装表示問題「消費者から『告発』期待〜食品表示110番〜」 週刊農林編集部(3/5号)
 「『農場から食卓』守るEUの食品安全行政」 週刊農林編集部(2/25号) 「『農場から食卓』守るEUの食品安全行政」 週刊農林編集部(2/25号) |
| |
| |
  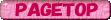 |