| |
| |
| |
国際・貿易  |
| |
| 〜〜2009年発行〜〜 |
| |
 解説「世界に向けた国産農林水産物輸出戦略」週刊農林編集部(7/15号) 解説「世界に向けた国産農林水産物輸出戦略」週刊農林編集部(7/15号)
 解説「農林水産物等の輸出取組事例100選」週刊農林編集部(7/15号) 解説「農林水産物等の輸出取組事例100選」週刊農林編集部(7/15号)
 「オバマ政権の農業通商戦略の展望」<農林抄>東京農業大学客員教授白岩 宏(2/25号) 「オバマ政権の農業通商戦略の展望」<農林抄>東京農業大学客員教授白岩 宏(2/25号)
 「オバマ政権と今後のWTO農業交渉」<農林抄>青山学院大学経営学部長岩田伸人(2/15号) 「オバマ政権と今後のWTO農業交渉」<農林抄>青山学院大学経営学部長岩田伸人(2/15号)
 「世界食料需給モデルによる10年後の予測結果」<1〜2>週刊農林編集部(1/25号・2/25号) 「世界食料需給モデルによる10年後の予測結果」<1〜2>週刊農林編集部(1/25号・2/25号) |
| |
| 〜〜2008年発行〜〜 |
| |
 「農業大国として注目集めるブラジル」<1〜連載中>
東京農工大学講師
山田祐彰(12/5号) 「農業大国として注目集めるブラジル」<1〜連載中>
東京農工大学講師
山田祐彰(12/5号)
 「20世紀末から中国は食料輸出国へ」<1〜2>
農林中金総合研究所副主任研究員
阮 蔚(12/5号・12/25号) 「20世紀末から中国は食料輸出国へ」<1〜2>
農林中金総合研究所副主任研究員
阮 蔚(12/5号・12/25号)
 解説「海外食料需給レポート2007」
<1〜連載中>週刊農林編集部(4/5号) 解説「海外食料需給レポート2007」
<1〜連載中>週刊農林編集部(4/5号) |
| |
| |
| 〜〜2007年発行〜〜 |
| |
 解説「コメ等11重点品目を重点国定め輸出拡大」 週刊農林編集部(7/15号) 解説「コメ等11重点品目を重点国定め輸出拡大」 週刊農林編集部(7/15号)
 解説「FTA農業交渉戦略の構築と展開」 週刊農林編集部(3/25号) 解説「FTA農業交渉戦略の構築と展開」 週刊農林編集部(3/25号) |
| |
| 〜〜2006年発行〜〜 |
| |
 「最新中国の農村・農業事情」 元国民経済研究協会理事長
叶 芳和(11/25号) 「最新中国の農村・農業事情」 元国民経済研究協会理事長
叶 芳和(11/25号)
 「WTO交渉決裂と今後に向けて」<1〜2>東京大学教授 鈴木宣弘(10/15号・10/25号) 「WTO交渉決裂と今後に向けて」<1〜2>東京大学教授 鈴木宣弘(10/15号・10/25号)
 「WTO農業交渉と品目横断的政策」週刊農林編集部 (5/25号) 「WTO農業交渉と品目横断的政策」週刊農林編集部 (5/25号)
 「WTO農業交渉と品目横断的政策」
農業評論家
土門 剛(1/15号) 「WTO農業交渉と品目横断的政策」
農業評論家
土門 剛(1/15号)
 解説「WTO香港閣僚会議と閣僚宣言」 週刊農林編集部 (1/15号) 解説「WTO香港閣僚会議と閣僚宣言」 週刊農林編集部 (1/15号) |
| |
| |
| 〜〜2005年発行〜〜 |
| |
 WTO農業交渉再開後の論点・争点「輸出国が上限関税70〜100%提案」 週刊農林編集部 (11/5号) WTO農業交渉再開後の論点・争点「輸出国が上限関税70〜100%提案」 週刊農林編集部 (11/5号)
 WTO農業交渉7月末プロセス「モダリティ叩き台提示断念」」
週刊農林編集部 (8/25号) WTO農業交渉7月末プロセス「モダリティ叩き台提示断念」」
週刊農林編集部 (8/25号)
 「オールジャパンで輸出拡大全国組織旗揚げ〜農林水産物等輸出促進全国協議会〜」
週刊農林編集部 (5/25号) 「オールジャパンで輸出拡大全国組織旗揚げ〜農林水産物等輸出促進全国協議会〜」
週刊農林編集部 (5/25号) |
| |
| |
| 〜〜2004年発行〜〜 |
| |
 「WTOの枠組み合意の評価と国内政策の方向性」<1〜4> 九州大学大学院教授
鈴木宣弘(10/15号・11/15号・12/5号・12/25号) 「WTOの枠組み合意の評価と国内政策の方向性」<1〜4> 九州大学大学院教授
鈴木宣弘(10/15号・11/15号・12/5号・12/25号)
 概説 「WTO交渉枠組み合意」 週刊農林編集部(8/25号) 概説 「WTO交渉枠組み合意」 週刊農林編集部(8/25号)
 「WTO農業枠組み合意と日本の採るべき方向」
経済産業研究所上席研究員
山下一仁(8/25号) 「WTO農業枠組み合意と日本の採るべき方向」
経済産業研究所上席研究員
山下一仁(8/25号)
 農林水産物輸出戦略「中国市場の分析と戦略」<1〜> 週刊農林編集部(8/5号) 農林水産物輸出戦略「中国市場の分析と戦略」<1〜> 週刊農林編集部(8/5号)
 「FTAを市民運動はどう考えるか」 脱WTO草の根キャンペーン事務局長
大野和興(4/25号) 「FTAを市民運動はどう考えるか」 脱WTO草の根キャンペーン事務局長
大野和興(4/25号)
 「WTOの原則と日本のFTA設立交渉」<1〜2> 青山学院大学WTO研究センター客員研究員
高瀬 保(4/25号・6/15号) 「WTOの原則と日本のFTA設立交渉」<1〜2> 青山学院大学WTO研究センター客員研究員
高瀬 保(4/25号・6/15号)
 「日−タイFTA:日本−アジア型FTAを」 東洋大学教授
服部信司(4/5号) 「日−タイFTA:日本−アジア型FTAを」 東洋大学教授
服部信司(4/5号)
 「日韓自由貿易協定における農林水産物の取扱い」<2〜5> 九州大学大学院教授
鈴木宣弘(4/5号・5/25号・6/15号・6/25号) 「日韓自由貿易協定における農林水産物の取扱い」<2〜5> 九州大学大学院教授
鈴木宣弘(4/5号・5/25号・6/15号・6/25号)
 「日本・アジアFTA農業交渉戦略について」 東京農業大学客員教授
白岩 宏(4/5号) 「日本・アジアFTA農業交渉戦略について」 東京農業大学客員教授
白岩 宏(4/5号)
 概説「日本・メキシコ経済連携協定大筋合意」 週刊農林編集部(4/5号) 概説「日本・メキシコ経済連携協定大筋合意」 週刊農林編集部(4/5号) |
| |
| |
| 〜〜2003年発行〜〜 |
| |
 「日韓FTA農業交渉戦略構築」<1> 九州大学大学院助教授
鈴木宣弘(12/25号) 「日韓FTA農業交渉戦略構築」<1> 九州大学大学院助教授
鈴木宣弘(12/25号)
 「農林水産物輸出戦略の構築と展開」<1> 週刊農林編集部(12/5号) 「農林水産物輸出戦略の構築と展開」<1> 週刊農林編集部(12/5号)
 「FTA交渉で強硬姿勢貫くメキシコの養豚事情」週刊農林編集部(11/15号) 「FTA交渉で強硬姿勢貫くメキシコの養豚事情」週刊農林編集部(11/15号)
 「日墨FTA交渉合意できず」週刊農林編集部(11/5号) 「日墨FTA交渉合意できず」週刊農林編集部(11/5号)
 「カンクン会議最強硬派ブラジルの農業新事情」農林水産政策研究所企画連絡室主任研究官
清水純一(10/25号) 「カンクン会議最強硬派ブラジルの農業新事情」農林水産政策研究所企画連絡室主任研究官
清水純一(10/25号)
 「WTOカンクン閣僚会議の決裂を受けて」九州大学大学院助教授
鈴木宣弘(10/5号) 「WTOカンクン閣僚会議の決裂を受けて」九州大学大学院助教授
鈴木宣弘(10/5号)
 「カンクン閣僚会議の顛末と今後の課題」安全な食と環境を考えるネットワーク事務局 伊庭みか子(10/5号) 「カンクン閣僚会議の顛末と今後の課題」安全な食と環境を考えるネットワーク事務局 伊庭みか子(10/5号)
 「WTOカンクン閣僚会議決裂」週刊農林編集部(10/5号) 「WTOカンクン閣僚会議決裂」週刊農林編集部(10/5号)
 「WTO農業交渉合意に向けた米国・EU妥協案、EUのCAP改革」週刊農林編集部(8/25号) 「WTO農業交渉合意に向けた米国・EU妥協案、EUのCAP改革」週刊農林編集部(8/25号)
 「モダリティをどう提案していくか」九州大学大学院助教授
鈴木宣弘(2/15号) 「モダリティをどう提案していくか」九州大学大学院助教授
鈴木宣弘(2/15号) |
| |
| |
| 〜〜2002年発行〜〜 |
| |
 「WTO規定の大いなる誤解」<1〜2> 九州大学大学院助教授
鈴木宣弘(7/5号・7/15号) 「WTO規定の大いなる誤解」<1〜2> 九州大学大学院助教授
鈴木宣弘(7/5号・7/15号)
 「白岩プランの実行を」宮城大学大学院教授
大泉一貫(3/25号) 「白岩プランの実行を」宮城大学大学院教授
大泉一貫(3/25号)
 「日本農業は輸出産業にはなりえない」和光大学名誉教授
持田恵三(3/25号) 「日本農業は輸出産業にはなりえない」和光大学名誉教授
持田恵三(3/25号)
 「中国の米輸出戦略にどう対応するか」<1〜3> 九州大学大学院教授
村田 武(3/5号・3/15号・3/25号) 「中国の米輸出戦略にどう対応するか」<1〜3> 九州大学大学院教授
村田 武(3/5号・3/15号・3/25号) |
| |
| |
| 〜〜2001年発行〜〜 |
| |
 「WTOドーハ閣僚会議が新ラウンド開始を宣言」
週刊農林編集部(12/5号) 「WTOドーハ閣僚会議が新ラウンド開始を宣言」
週刊農林編集部(12/5号) |
 「WTO閣僚会議の評価と今後の農業交渉戦略」元GATT事務局交渉官
高瀬 保(12/5号) 「WTO閣僚会議の評価と今後の農業交渉戦略」元GATT事務局交渉官
高瀬 保(12/5号) |
 「農業宣言を起点に本格交渉始まる」東洋大学教授
服部信司(12/5号) 「農業宣言を起点に本格交渉始まる」東洋大学教授
服部信司(12/5号) |
| |
| |
| 〜〜2000年発行〜〜 |
| |
 「アメリカの農業交渉提案と我が国のとるべき立場」東洋大学教授
服部信司(11月5日号) 「アメリカの農業交渉提案と我が国のとるべき立場」東洋大学教授
服部信司(11月5日号)
 「米国案の評価と日本の立場」東洋大学教授
高瀬 保(11月5日号) 「米国案の評価と日本の立場」東洋大学教授
高瀬 保(11月5日号)
 「EUのWTO交渉戦略と日本農業」宇都宮大学教授
是永東彦(3月5日号) 「EUのWTO交渉戦略と日本農業」宇都宮大学教授
是永東彦(3月5日号)
 「WTOシアトル会議について」日本消費者連盟副運営委員長
山浦康明(2月15日号) 「WTOシアトル会議について」日本消費者連盟副運営委員長
山浦康明(2月15日号)
 「シアトル会議凍結は成功」東京農工大学学長 梶井 功(2月5日号) 「シアトル会議凍結は成功」東京農工大学学長 梶井 功(2月5日号)
 「WTO農業交渉への全日農の主張」全日本農民組合連合会委員長 谷本 巍(1月15日号) 「WTO農業交渉への全日農の主張」全日本農民組合連合会委員長 谷本 巍(1月15日号)
 「NGOはシアトル会議で行動した」安全な食と環境を考えるネットワーク事務局 伊庭みか子(1月15日号) 「NGOはシアトル会議で行動した」安全な食と環境を考えるネットワーク事務局 伊庭みか子(1月15日号)
 「WTO農業協定と日本の稲作農業<1〜2>」社会基盤研究所主任研究員
藤澤研二(新年号・2月15日号) 「WTO農業協定と日本の稲作農業<1〜2>」社会基盤研究所主任研究員
藤澤研二(新年号・2月15日号)
 「WTO閣僚会合決裂とその背景<1〜3>」東洋大学教授 服部信司(新年号・2月5日号・25日号) 「WTO閣僚会合決裂とその背景<1〜3>」東洋大学教授 服部信司(新年号・2月5日号・25日号)
 「GATT/WTOが果たしてきた役割<1〜3>」東海大学教授
高瀬 保(新年号・2月5日号・25日号) 「GATT/WTOが果たしてきた役割<1〜3>」東海大学教授
高瀬 保(新年号・2月5日号・25日号)
 「新たなコンセンサスを求めて<1〜2>」三井物産顧問 白岩 宏(新年号・1月15日号) 「新たなコンセンサスを求めて<1〜2>」三井物産顧問 白岩 宏(新年号・1月15日号)
 「決裂したWTO閣僚会議」東京大学大学院教授
生源寺真一(新年号) 「決裂したWTO閣僚会議」東京大学大学院教授
生源寺真一(新年号)
 「WTO閣僚会議決裂の意味するもの<1〜3>」東京大学名誉教授 佐伯尚美(新年号・1月15日号・2月15日号) 「WTO閣僚会議決裂の意味するもの<1〜3>」東京大学名誉教授 佐伯尚美(新年号・1月15日号・2月15日号)
 「シアトル閣僚会議と次期WTO対策」島根大学名誉教授 安達生恒(新年号) 「シアトル閣僚会議と次期WTO対策」島根大学名誉教授 安達生恒(新年号)
 「シアトル閣僚会議と今後の農業交渉」農林水産審議官
熊澤英明(新年号) 「シアトル閣僚会議と今後の農業交渉」農林水産審議官
熊澤英明(新年号) |
| |
| |
  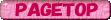 |