国際・貿易  |
| |
 |
| |
| |
 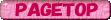 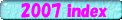 |
| |
| |
| |
| |
農業政策  |
| |
 「消費者・環境視点からの生産調整政策への転換を」
高崎経済大学学長 吉田俊幸(12/25号) 「消費者・環境視点からの生産調整政策への転換を」
高崎経済大学学長 吉田俊幸(12/25号)
 「はびこる偽装表示と法律」
食の安全・監視市民委員会代表
神山美智子(12/5号) 「はびこる偽装表示と法律」
食の安全・監視市民委員会代表
神山美智子(12/5号)
 「有機農業推進法成立1年後の政策課題」
民間稲作研究所代表 稲葉光國(11/15号) 「有機農業推進法成立1年後の政策課題」
民間稲作研究所代表 稲葉光國(11/15号)
 「有機農業推進法に期待する」
有機農業推進協会事務局長
白根節子(11/5号) 「有機農業推進法に期待する」
有機農業推進協会事務局長
白根節子(11/5号)
 「米づくりが続けられない!」
農民運動全国連合会事務局長
笹渡義夫(10/25号) 「米づくりが続けられない!」
農民運動全国連合会事務局長
笹渡義夫(10/25号)
 「地域でのエネルギー自給の試み」
岩手県奥州市地域エネルギー推進室長
菅原 浩(10/15号) 「地域でのエネルギー自給の試み」
岩手県奥州市地域エネルギー推進室長
菅原 浩(10/15号)
 「養殖クロマグロ供給を目指す人工孵化技術」
近畿大学水産研究所大学院准教授
澤田好史(10/5号) 「養殖クロマグロ供給を目指す人工孵化技術」
近畿大学水産研究所大学院准教授
澤田好史(10/5号)
 「「農地政策の見直し」への論評」
東北大学大学院農学研究科長・教授
工藤昭彦(9/25号) 「「農地政策の見直し」への論評」
東北大学大学院農学研究科長・教授
工藤昭彦(9/25号)
 「雑音に惑わされず改革に邁進を」
江戸川大学経営社会学科教授
藤澤研二(9/15号) 「雑音に惑わされず改革に邁進を」
江戸川大学経営社会学科教授
藤澤研二(9/15号)
 「バイオディーゼル燃料の利用推進に向けて」
日本有機資源協会専務理事
今井伸治(9/5号) 「バイオディーゼル燃料の利用推進に向けて」
日本有機資源協会専務理事
今井伸治(9/5号)
 「南西諸島におけるバイオマス持続的利用技術」
農村工学研究所農地工学研究室長
凌 祥之(8/25号) 「南西諸島におけるバイオマス持続的利用技術」
農村工学研究所農地工学研究室長
凌 祥之(8/25号)
 「『イネイネ・日本』プロジェクト立上げ」
プロジェクト代表 森田茂紀(8/5号) 「『イネイネ・日本』プロジェクト立上げ」
プロジェクト代表 森田茂紀(8/5号)
 「国産バイオ燃料生産拡大目標達成に向けた展開」
農水省環境政策課長 西郷正道(7/25号) 「国産バイオ燃料生産拡大目標達成に向けた展開」
農水省環境政策課長 西郷正道(7/25号)
 「経営サポートする専門家育成を」
江戸川大学経営社会学科教授
藤澤研二(7/5号) 「経営サポートする専門家育成を」
江戸川大学経営社会学科教授
藤澤研二(7/5号)
 「担い手の意向尊重される面的集積組織の制度設計を」
日本農業法人協会常務
稲垣照哉(6/15号) 「担い手の意向尊重される面的集積組織の制度設計を」
日本農業法人協会常務
稲垣照哉(6/15号)
 「研究独法バイオ燃料研究開発に向けて」
バイオマス研究センター長
片山秀策(6/5号) 「研究独法バイオ燃料研究開発に向けて」
バイオマス研究センター長
片山秀策(6/5号)
 「表現しなければ「環境支払い」にならない」
農と自然の研究所代表
宇根 豊(5/25号) 「表現しなければ「環境支払い」にならない」
農と自然の研究所代表
宇根 豊(5/25号)
 「有機農業第Ⅱ世紀の始まりに」
茨城大学農学部教授 中島紀一(5/15号) 「有機農業第Ⅱ世紀の始まりに」
茨城大学農学部教授 中島紀一(5/15号)
 「養豚協会が麹菌利用した飼養に取組み」
日本養豚協会常務 伊藤政美(4/15号) 「養豚協会が麹菌利用した飼養に取組み」
日本養豚協会常務 伊藤政美(4/15号)
 「エコフィードの現状と展開方向」
日本大学生物資源科学部教授
阿部 亮(4/5号) 「エコフィードの現状と展開方向」
日本大学生物資源科学部教授
阿部 亮(4/5号)
 「チーズ向け拡大に期待と不安!」
北海道農民連盟事務局次長
久須田洋治(3/25号) 「チーズ向け拡大に期待と不安!」
北海道農民連盟事務局次長
久須田洋治(3/25号)
 「有機農業推進基本方針への補強」
京都精華大講師 本野一郎(3/15号) 「有機農業推進基本方針への補強」
京都精華大講師 本野一郎(3/15号)
 「野草資源を活用する放牧PR大作戦を」
フリージャーナリスト
吉田光宏(3/5号) 「野草資源を活用する放牧PR大作戦を」
フリージャーナリスト
吉田光宏(3/5号)
 「団塊世代と若者は放牧を!」
お米の勉強会代表 村山日南子(2/25号) 「団塊世代と若者は放牧を!」
お米の勉強会代表 村山日南子(2/25号)
 「有機農業推進方針策定に向けた提案」
遺伝毒性を考える集い代表
亘 昌子(2/15号) 「有機農業推進方針策定に向けた提案」
遺伝毒性を考える集い代表
亘 昌子(2/15号)
 「鶏インフルエンザは人間への警鐘」
農政ジャーナリスト 横田哲治(2/5号) 「鶏インフルエンザは人間への警鐘」
農政ジャーナリスト 横田哲治(2/5号)
 「2007年度予算と食料自給率」
東京大学教授 鈴木宣弘(1/25号) 「2007年度予算と食料自給率」
東京大学教授 鈴木宣弘(1/25号)
 「飼料の自給をめざして」
元五嶋牧場代表 五嶋和七(1/15号) 「飼料の自給をめざして」
元五嶋牧場代表 五嶋和七(1/15号)
 「有機農業推進法の成立を受けて」
農水省環境保全型農業対策室長
栗原 眞(1/5号) 「有機農業推進法の成立を受けて」
農水省環境保全型農業対策室長
栗原 眞(1/5号) |
| |
| |
 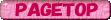 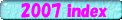 |
| |
| |
| |
| |
林業政策  |
| |
 「都会にログハウスを」
日本ログハウス協会事務局長
小坂博美(11/25号) 「都会にログハウスを」
日本ログハウス協会事務局長
小坂博美(11/25号)
 「森林セラピーを核にした地域振興」
上松町役場まちづくり推進室係長
見浦 崇(7/15号) 「森林セラピーを核にした地域振興」
上松町役場まちづくり推進室係長
見浦 崇(7/15号) |
| |
 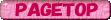 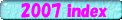 |
| |
| |
| |
| |
水産政策  |
| |
 「養殖クロマグロ供給を目指す人工孵化技術」
近畿大学水産研究所大学院准教授
澤田好史(10/5号) 「養殖クロマグロ供給を目指す人工孵化技術」
近畿大学水産研究所大学院准教授
澤田好史(10/5号)
 「魚介類の消費減因分析不十分」
鹿児島大学水産学部准教授
佐久間美明(6/25号) 「魚介類の消費減因分析不十分」
鹿児島大学水産学部准教授
佐久間美明(6/25号)
 「漁業構造改革のゆくえと消費者」
広島大学生物生産学部教授
山尾政博(4/25号) 「漁業構造改革のゆくえと消費者」
広島大学生物生産学部教授
山尾政博(4/25号) |
| |
 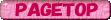 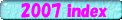 |
| |
 |
