国際・貿易  |
| |
 「決裂したWTOドーハラウンド交渉の含意」 東京農業大学客員教授
白岩 宏(9/5号) 「決裂したWTOドーハラウンド交渉の含意」 東京農業大学客員教授
白岩 宏(9/5号) |
| |
| |
 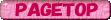 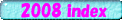 |
| |
| |
| |
| |
農業政策  |
| |
 「国民の利益につながる真の政策を」 農業評論家
土門 剛(12/25号) 「国民の利益につながる真の政策を」 農業評論家
土門 剛(12/25号)
 「野菜消費の需要変化と生産技術開発」 野菜茶業研究所業務用野菜研究チーム長
東尾久雄(12/5号) 「野菜消費の需要変化と生産技術開発」 野菜茶業研究所業務用野菜研究チーム長
東尾久雄(12/5号)
 「ガンの死亡者はなぜ増えるのか -農と食の視点から-」 FSN代表
横田哲治(11/25号) 「ガンの死亡者はなぜ増えるのか -農と食の視点から-」 FSN代表
横田哲治(11/25号)
 「JGAP基本方針と今後の展望」 日本GAP協会専務理事
武田泰明(10/15号) 「JGAP基本方針と今後の展望」 日本GAP協会専務理事
武田泰明(10/15号)
 「非食用米・事故米の市場流通を支える減反政策」 遺伝毒性を考える集い代表
亘 昌子(10/5号) 「非食用米・事故米の市場流通を支える減反政策」 遺伝毒性を考える集い代表
亘 昌子(10/5号)
 「自給率向上に向けた野菜戦略」 東京農業大学教授
藤島廣二(9/25号) 「自給率向上に向けた野菜戦略」 東京農業大学教授
藤島廣二(9/25号)
 「食糧危機に備え『my米備蓄』」 食政策センター・ビジョン21代表
安田節子(9/15号) 「食糧危機に備え『my米備蓄』」 食政策センター・ビジョン21代表
安田節子(9/15号)
 「農業は日本のソフトパワー」 帝京平成大学教授
叶 芳和(8/5号) 「農業は日本のソフトパワー」 帝京平成大学教授
叶 芳和(8/5号)
 「新たな食料安全保障の構築」 農林水産省大臣官房食料安全保障課長
末松広行(夏季特集号) 「新たな食料安全保障の構築」 農林水産省大臣官房食料安全保障課長
末松広行(夏季特集号)
 「どこまでできるか
消費者行政改革」 食の安全・監視市民委員会代表、弁護士
神山美智子(7/15号) 「どこまでできるか
消費者行政改革」 食の安全・監視市民委員会代表、弁護士
神山美智子(7/15号)
 「世界の食糧問題とDNA研究」 かずさDNA研究所主任研究員
磯部祥子(6/15号) 「世界の食糧問題とDNA研究」 かずさDNA研究所主任研究員
磯部祥子(6/15号)
 「四川大地震、中国農業生産への影響」 中国社会科学院農村発展研究所博士研究員
曹 斌(5/25号) 「四川大地震、中国農業生産への影響」 中国社会科学院農村発展研究所博士研究員
曹 斌(5/25号)
 「飼料米振興に向けた課題」<1〜2>
東京農業大学農学部准教授 信岡誠治(4/25号・6/25号) 「飼料米振興に向けた課題」<1〜2>
東京農業大学農学部准教授 信岡誠治(4/25号・6/25号)
 「放牧酪農が日本酪農を救う」
酪農学園大学教授 荒木和秋(4/15号) 「放牧酪農が日本酪農を救う」
酪農学園大学教授 荒木和秋(4/15号)
 「遺伝子組換え作物栽培に期待する」
バイオ作物懇話会代表
長友勝利(4/5号) 「遺伝子組換え作物栽培に期待する」
バイオ作物懇話会代表
長友勝利(4/5号)
 「食品行政一元化の行方を追う」
日本消費者連盟事務局長
水原博子(3/25号) 「食品行政一元化の行方を追う」
日本消費者連盟事務局長
水原博子(3/25号)
 「アジアの水田の『多様な生産力』と『囲い込み』」」
全国合鴨水稲会世話人代表
古野隆雄(3/15号) 「アジアの水田の『多様な生産力』と『囲い込み』」」
全国合鴨水稲会世話人代表
古野隆雄(3/15号)
 「バイオ燃料と米国の食料戦略」」
市民バイオテクノロジー情報室代表
天笠啓祐(3/5号) 「バイオ燃料と米国の食料戦略」」
市民バイオテクノロジー情報室代表
天笠啓祐(3/5号)
 「学校給食を地産地消の「食育」の場に」
お米の勉強会代表 村山日南子(2/25号) 「学校給食を地産地消の「食育」の場に」
お米の勉強会代表 村山日南子(2/25号)
 「食品安全の欺瞞―ブルータスお前もか―」
全国獣医事協議会会長
八竹昭夫(1/25号) 「食品安全の欺瞞―ブルータスお前もか―」
全国獣医事協議会会長
八竹昭夫(1/25号)
 「農産物直売所を中心に農村資源の有機的活用を」
農村開発リサーチ代表取締役
田中 満(1/15号) 「農産物直売所を中心に農村資源の有機的活用を」
農村開発リサーチ代表取締役
田中 満(1/15号)
 「農林水産分野における知的財産戦略」
農水省大臣官房参事官
松原明紀(新年号) 「農林水産分野における知的財産戦略」
農水省大臣官房参事官
松原明紀(新年号) |
| |
| |
 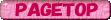 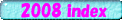 |
| |
| |
| |
| |
林業政策  |
| |
 「林業に公平な市場は存在するか」 森林技術総合研修所長
小原文悟(10/25号) 「林業に公平な市場は存在するか」 森林技術総合研修所長
小原文悟(10/25号)
 「秋田新生産システム事業への期待と課題」秋田県立大学木材高度加工研究所教授
高田克彦(5/15号) 「秋田新生産システム事業への期待と課題」秋田県立大学木材高度加工研究所教授
高田克彦(5/15号) |
| |
 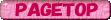 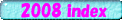 |
| |
| |
| |
| |
水産政策  |
| |
 「ウナギの産卵生態解明に向けて」 中央水産研究所浅海生態系研究室長
張 成年(10/15号) 「ウナギの産卵生態解明に向けて」 中央水産研究所浅海生態系研究室長
張 成年(10/15号)
 「有明海再生のために不可欠な諫早湾開門」 諫早干潟緊急救済本部・東京事務所
青木智弘(8/25号) 「有明海再生のために不可欠な諫早湾開門」 諫早干潟緊急救済本部・東京事務所
青木智弘(8/25号)
 「燃油高騰に対する漁業経営支援策」
東京大学社会科学研究所教授
加瀬和俊(7/5号) 「燃油高騰に対する漁業経営支援策」
東京大学社会科学研究所教授
加瀬和俊(7/5号)
 「日本水産業再生へIQ制導入を」
政策研究大学院大学教授
小松正之(6/5号) 「日本水産業再生へIQ制導入を」
政策研究大学院大学教授
小松正之(6/5号)
 「南極海鯨類捕獲調査」
日本鯨類研究所理事長
森本 稔(2/15号) 「南極海鯨類捕獲調査」
日本鯨類研究所理事長
森本 稔(2/15号)
 「MELジャパンは水産界をアピールするチャンス」
ウーマンズフォーラム魚代表
白石ユリ子(2/5号) 「MELジャパンは水産界をアピールするチャンス」
ウーマンズフォーラム魚代表
白石ユリ子(2/5号) |
| |
 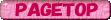 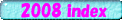 |
| |
 |
